※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています
最近、助成金の不正受給に関わった社労士が公表されたというニュースが報じられています。
助成金狙う悪徳社労士、コロナ禍の「雇調金バブル」で相次ぐ…3年間で64人が関与・刑事事件にもhttps://www.yomiuri.co.jp/national/20250923-OYT1T50118/
この事件では、詐欺罪で罪に問われていますね。
社労士の女、コロナ雇調金不正で3000万円詐取か…1申請で手数料8万円と受給額の2割https://www.yomiuri.co.jp/national/20230110-OYT1T50177
このようなケースでは、社労士としての信頼を失うだけでなく、「懲戒処分」「失格処分」という重い責任を負う可能性があります。
. 懲戒処分・失格処分の制度と事例
社労士が不正関与等で処分を受ける際には、社会保険労務士法に基づく懲戒処分規定が適用されます。具体的な流れと可能性のある処分を以下に整理します。
過去問や、試験問題でも問われることもある論点ですので、まずは基本となる処分をチェック。
懲戒処分の種類(社労士法上)
社会保険労務士法第25条などで、以下のような懲戒処分が定められています。
- 戒告
最も軽微な処分。氏名や処分理由が公告される。 - 業務停止
一定期間、社労士として業務を停止される。停止期間中は業務を行えない。 - 失格
社労士資格そのものを剥奪(登録を抹消)する処分。
この処分は、厚生労働大臣により行われ、官報や厚労省サイトなどで公告されます。
公表事例・最近の処分傾向
- 令和6年3月11日には、助成金不正関与の事案で3名の社労士に対して 1年の業務停止 が処分されたという公告がありました。 PSRN
- 全国社労士会連合会の懲戒処分事例リストでは、近年「失格処分」を受けた社労士も複数存在しています。 社会保険労務士.jp
- 大阪の事例では、社労士が助成金不正関与を理由に、支給取消・返還命令を受けたものが公表されています。 県労働局所在地一覧
つまり、助成金不正関与が確認されれば、業務停止・失格といった重たい処分を受ける可能性が十分にあるのが実情です。
官報公告などで、全てフルネームでの実名でネット上に公開されることになり、再起を図る時に多大な障壁となるでしょう。
さきほどの助成金狙う悪徳社労士、コロナ禍の「雇調金バブル」で相次ぐ…3年間で64人が関与・刑事事件に、の記事内でも、「失格」や業務停止の処分など重いものもあります。
異業種交流会・女性社労士…
手続きの簡素化に乗じた虚偽申請も相次ぎ、今年6月までに判明した特例措置期間の不正受給の総額は1044億円超に上る。助成金の2割程度が相場とされる報酬目当てに不正に関わる社労士が続出したとみられ、ある労働局の担当者は「申請書に不備がなければ基本的に支給を認めざるをえない。記載が簡略化された書類で偽造を見抜くのは難しい」という状況を利用し、社労士として雇調金など計約3250万円の不正受給に関与したとして詐欺罪に問われた元被告の女性は昨年2月、東京地裁から懲役4年6月の実刑判決を言い渡され、確定した。
女性は異業種交流会などで知り合った経営者らに、「売り上げが下がった会社がもらえる助成金があり、社員の給料を全てもらえる」などと不正を指南し、手数料に加えて受給額の2割を報酬として得ていた。判決では「国家資格と専門知識を悪用し、社労士に対する社会的信頼も損なったと言わざるをえない」と不正を厳しく批判されたとしています。
異業種交流会というのは経営者の集まりなどで行われることが多く、参加者は男性が大多数、女性の社労士(士業)が参加するだけで注目を集めることも多いです。
あまりにも悪質で、濡れ手で粟の状況だったのではないかと…
失格になるかどうかの判断要素
「不正受給の関与=必ず失格」というわけではなく、以下要素が判断材料になります。
- 関与の度合い・役割(指揮・設計か、単なる書類作成か、チェックの有無か)
- 故意性の有無(知らなかった、誤認したという主張が認められるか)
- 被害額・不正規模の大きさ
- 過去の処分歴・前科歴
- 処分後の反省・再発防止策の有無
実際、軽微な過失・関与であれば「業務停止」・「戒告」で済むこともありますが、悪質性が強いと「失格処分」に至る可能性があります。
社労士側から持ち掛けたのであれば失格処分、経営者とアイディアを出し合って、虚偽の書類(存在しない従業員でとか)を作成だと業務停止何か月か、経営者の言い分を丸のみして(休んでない従業員を休業扱いでとか)書類作成で実は虚偽だった・・・だと難しいところですが戒告か業務停止か・・・みたいな。
懲戒処分などについての過去問もチェックしていきましょう。
抜粋した過去問(問題文要旨+正答・解説)
※各設問は「社一(社会保険に関する一般常識)/労一(労働に関する一般常識)」など出題区分が異なります。以下は「懲戒処分(社労士法)に関する出題」のうち、戒告・業務停止・失格に直接関係する設問を抜粋しています。各設問の出典を末尾に記載します(もっと原文を見たい場合は該当リンクを開いてください)。
1) 平成28年(2016) — 「相当の注意を怠った場合の懲戒」
問題(要旨)
開業社会保険労務士が「相当の注意を怠り」労働社会保険諸法令に違反する行為について指示・相談に応じたときは失格処分に処することができる(択一/○×形式)。
正答(要旨)
×
「戒告」又は「1年以内の業務停止」の処分があり得る(失格処分は原則ない)。
解説(要点)
社会保険労務士法上、故意(悪質な場合)に真正の事実に反して申請書等の作成等を行った場合は「業務停止又は失格」があり得るが、単に相当の注意を怠った場合はより軽い「戒告」または「1年以内の業務停止」に該当する条文解釈が出題のポイント。条文の「故意」と「相当の注意を怠る」の違いを押さえること。
2) 平成30年(2018) — 「重大な非行と処分の選択」
問題(要旨)
厚生労働大臣が、社労士に重大な非行があったと判断した場合、必ず失格処分となる(択一/○×形式)。
正答(要旨)
×
重大な非行が認められる場合に懲戒処分は可能であるが、必ずしも失格処分を必須とするわけではなく、事案の程度に応じ戒告・業務停止・失格のいずれかがあり得る(設問で「必ず失格にしなければならない」といった趣旨なら誤)。
解説(要点)
「重大な非行があったときは懲戒処分を下すことができる」→これは正しいが、処分の種類は裁量(事案の重さ)を考慮する点が論点。出題では“必ず失格”という言い回しが頻出の誤答トラップ。
3) 令和元年(2019) — 「社労士会の懲戒権限」
問題(要旨)
社会保険労務士会が、所属会員が法令に違反するおそれがあると認めた場合、懲戒処分に処することができる。(択一/○×形式)。
正答(要旨)
×
会は会則に従い、当該会員に対して(最終的に)社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分を申し出ることができる旨が問われました。(処分自体は主務大臣・厚生労働大臣の手続との関係がポイント)。
解説(要点)
社労士会は懲戒の実行主体(=最終判断をするのは主務大臣)ではないが、会則に従って懲戒手続きを進めることは出来る。通知・勧告・懲戒の提議等の手続きまで。試験では懲戒処分は、厚生労働大臣が行うことができるという点を押さえること。
4) 令和2年(2020) — 「業務停止の効果」
問題(要旨)
開業社労士が「1年以内の業務停止」の処分を受けた場合の実務上の帰結(受託契約・証票返還等)について、所定の期間、その業務を行うことができなくなるので、依頼者との間の受託契約を解除し、社会保険労務士証票も返還する義務が生ずる。(択一/○×形式)
正答(要旨)
〇
業務停止期間中は社会保険労務士としての業務を行えないため、依頼者との受託契約を解除したり、社労士証票を返還する必要がある。
解説(要点)
業務停止は資格行使の一時停止であり、業務遂行はできない。したがって契約関係や名義使用、証票管理など具体的対応を理解しておく。試験では「業務停止=資格行使停止」の実務的影響が問われる傾向にあります。
5) 令和4年(2022) — 「戒告の性格に関する誤答トラップ」
問題(要旨)
「戒告は本人の将来を戒めるため、1年以内の一定期間について資格や業務に制約を課す処分である」(択一/○×形式)。
正答(要旨)
誤り
戒告は口頭・文書での厳重注意的処分であり、資格に対する直接的な制約(例えば資格停止期間を課す)を意味するものではない。
解説(要点)
戒告は最も軽い懲戒であり、「資格の制約」を意味するかのような記述は誤り。1年以内の「業務停止」は資格行使を制限する実効的な制裁だが、戒告はそうではない点を混同しないこと。
6) 令和5年(2023)〜公式公告SAMPLE(実刑的案件ではないが実務理解に有用)
出典(公告要旨)
厚生労働省の懲戒処分公告では、実際に「故意に真正の事実に反して申請書の作成を行った」等で**業務停止(例:1年)**やその他処分が行われた事例が公示されている(処分名・期間・理由・登録番号等が公告される)。
キャリアアップ助成金の不正受給に関してのホームページ上で公開されている情報。
学習ポイント(要旨)
実際の公告は処分の「重さ」と「理由」がそのまま示されるので、試験学習だけでなく実務リスク把握にも必読。公告文から「どの程度の事実が失格や業務停止につながるか」が学べる。
社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第1項及び第25条の3の規定に基づき、令和5年3月18日から1年の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和5年4月3日
厚生労働大臣 加藤 勝信
記
社会保険労務士 光安 弘子
事務所の名称 光安会計・労務事務所
事務所の所在地 福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-1 DS福岡ビル4F
社会保険労務士登録番号 第40020074号
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32244.html?utm_source=chatgpt.com
懲戒処分の対象となった行為 故意に、真正の事実に反して申請書の作成を行ったこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと
こういった具体的な事例を目にすると、身が引き締まりますかね。学習においても具体的な物を目にしてから取り組むと、印象に残り易くなり、記憶の定着が良くなるでしょう。
過去問に改めて目を通した時にも脳裏に不正受給すると公開処刑される・・・と思い出して、どの程度の罪の重さとやらかし具合で業務停止となるか、今後の事例問題への反映なども踏まえて学習に取り組みましょう!
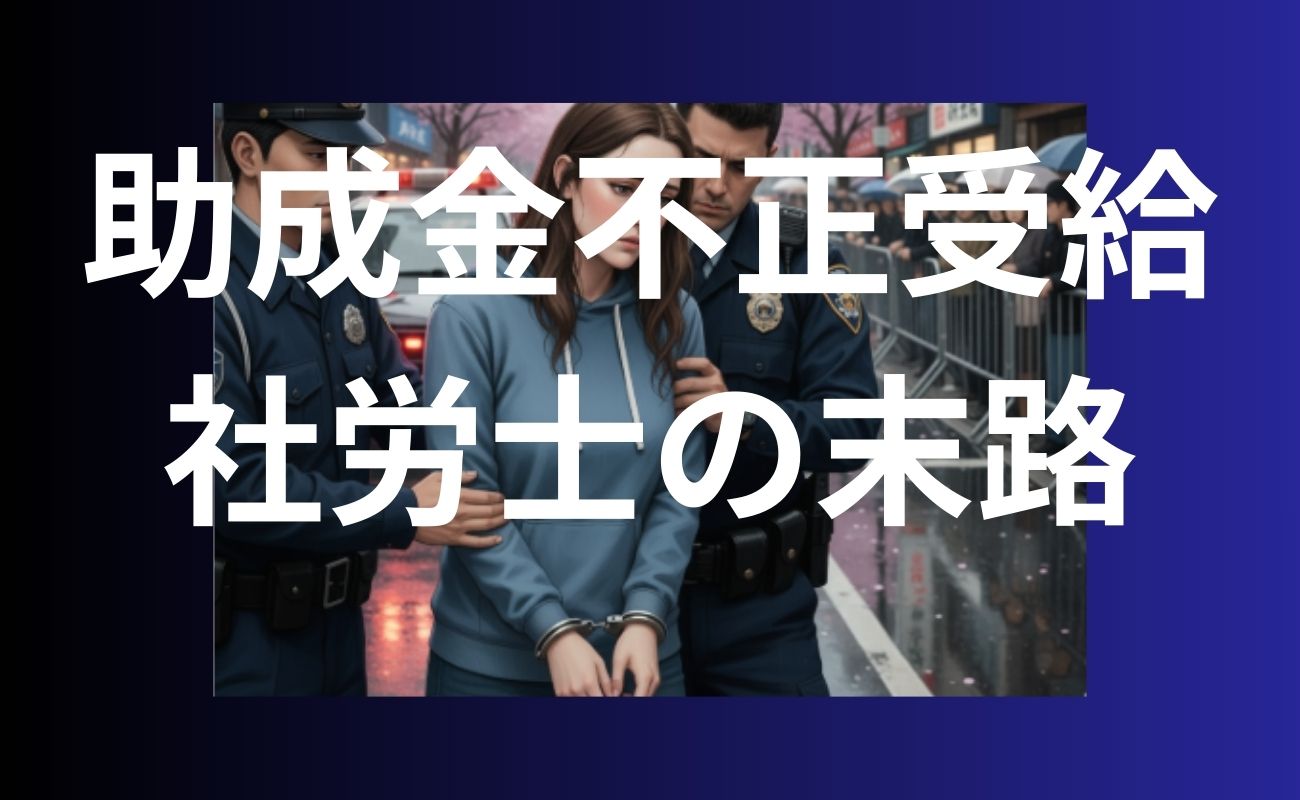
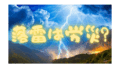

コメント