※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています
令和7年労災問1
今回ピックアップするのは労災保険の適用について、ほぼ毎年手を変え品を変え論点を色々ずらしたりで焼き直しをすることも多いところです。
労災保険の適用について正誤を判断。
R7−1~C
障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者は、雇用契約の締結の有無にかかわらず、労災保険法が適用される。
正解は・・・
×
これはH28年にも問われた論点でした。
過去問やってたら正解できた設問の一つとなりましょう。
回答詳細解説
この設問の解説をしていくと、まずは雇用契約の有無が労災保険法が適用に影響するかということ。
雇用契約を締結せずに就労継続支援を受ける障害者には、基本的に労災保険法が適用されませんよ、ということ。
労災保険法は労働者を使用する事業に適用されるのを基本とし、労働者として認められるのは、労働基準法の9条に規定する労働者と同じ、要するに、「労働者」を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定しています。かつて選択式R1の労災保険法の労働者は労働基準法上の労働者である、というのを問われたこともあったでしょう
いわゆる就労継続支援のA型となるものです。
労災保険の適用も準ずるものとして、雇用契約を締結しないのであれば労災は適用されず。
作業をしてて怪我をしてしまった場合には労災適用されず揉めそうですね(^_^;)
過去問参照
平成28年の設問でも障害者の就労継続支援についてです。
障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける障害者には、基本的には労災保険法が適用されない。
正解は、○
こちらは、就労継続支援B型に該当します。
補足・就労継続支援の労災適用・雇用契約
細かいところでは、就労継続支援A型とB型は「障害のある方が働く場所」という意味で同じではあるものの、労災適用においても違います。
就労継続支援A型は、一般企業などで働くことが困難なものの、雇用契約に基づいて働くことができる方が事業所と雇用契約を結んだうえで働くことができるサービスで労災の適用があるのがこちらです。
一方、就労継続支援B型は雇用契約を結ばずに、障害や体調にあわせて自分のペースで就労をする=指揮命令化で働くというわけではない、ということで労災の適用外になります。
今後の社労士試験の問題では特段A型やB型などの種別について掘り下げたりはしないと思うものの、長文化していくときの文字数でわかりにくくするために装飾文として添えられることもあるかもしれませんね。
頻出論点
労災の適用の可否については毎年のように問われる頻出論点です。
過去問でも早い段階で取り組むところでしょう。
次の試験では過去問の焼き直しで、正誤を逆転させて再出題されたりもあり得るし、選択式問題でも抜かれることもあるような基本的な事項ですので、しっかりと理解しましょう。
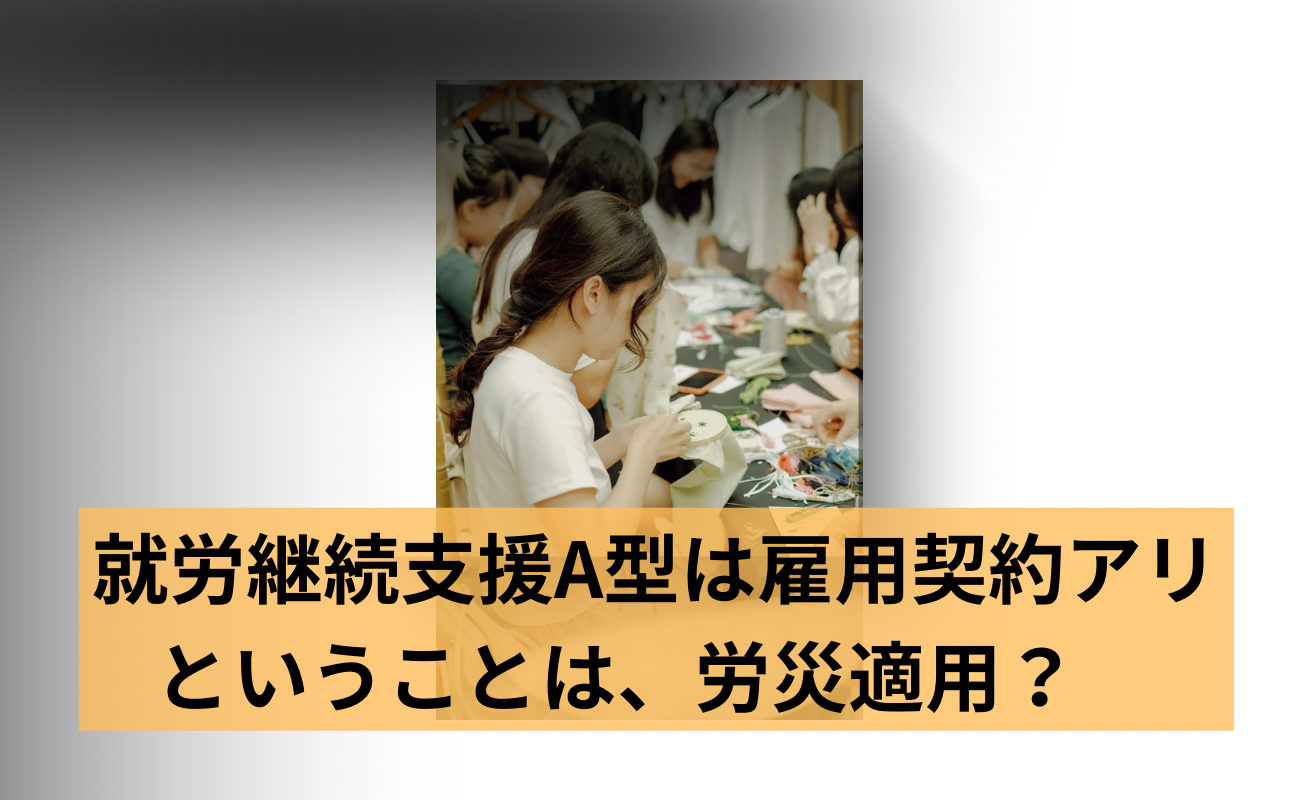
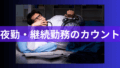
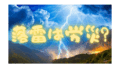
コメント