※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています
日本の労働法制において「年次有給休暇(以下:有給)」は、労働者の権利として強く保障されています。
しかし実務上、「この時期は忙しいから有給は取らせられない」といったやりとりも耳にしますよね。
そういう会社は大概ブラックだけど、会社の言い分もわからないこともない。
では、会社側はどのような条件で有給取得を拒否できるのか?
今回は、社労士試験の過去問で問われる知識をベースに、実際に役立つポイントを整理してみます。
年次有給休暇の原則
労働基準法第39条では、一定の勤続期間・出勤率を満たした労働者に有給が付与されます。
ここで重要なのは、労働者が時季を指定すれば、原則として会社はその取得を認めなければならない という点です。
- 付与される日数は勤続年数に応じて増加
- 半日単位・時間単位での取得も可能(労使協定が必要)
つまり、基本有給取得は「労働者の自由」。
ただし、会社側に全く拒否権がないわけではありません。
会社が有給を拒否できる唯一の理由 ― 「時季変更権」
会社が有給取得を制限できるのは 「時季変更権」 が認められている場合のみです。
時季変更権とは?
労基法第39条第5項に基づき、
事業の正常な運営を妨げる場合、会社は労働者の希望する有給休暇を取る日にちを変更できる
というルールです。
ポイントは「拒否」ではなく「変更」。
つまり「その日はダメだけど、この日なら休んでいいよ」という形で認めるものです。
社労士過去問で学ぶ「時季変更権」の範囲
実際の試験問題でも、よく問われる論点です。
- 過去問例①
「会社は繁忙期であれば常に有給を拒否できる」
正解は…
× 誤り。繁忙期=一律NG ではなく、事業運営に支障があるかどうか個別に判断 される。 - 過去問例②
「時季変更権を行使する場合、代替要員の確保などの努力を尽くした上でなければならない」
正解は…
○ 正しい。裁判例でも、企業側が努力をしてもなお支障が避けられない場合に限り有給休暇の時季変更が認められる。
実務でよくある「拒否できる・できない」の境界線
拒否(時季変更権行使)が認められるケース
- 繁忙期に同じ部署の多数が同時に休む → 業務が停止する
- 専門職など代替がきかず、休まれると安全面・生産面に重大な影響が出る
拒否できないケース
- 「人手が減るから困る」という抽象的な理由だけ
- 代替要員を探せば対応できるのに、その努力をしていない場合
- 社内ルールで「有給は事前に1か月前申請」と決めているが、法律上それを超える制限は無効
現実的に代替要員を探すというのもある程度の規模の会社でないと難しかったり、全然他部署で勝手がわからない人を連れてくるのも現実的ではないけどね・・・少ない人数で回そうとすると個々人の負担が増えるなど業務によっては影響大きいこともあるし、店や工場を閉めてしまうのも選択肢に考えないといけないのかも。
1カ月前にシフト締めきったから取得不可と言うような会社はブラック認定待ったナシです。
経営者さんや、シフト管理を行う店長さんなども注意が必要です。
注意したい実務ポイント
- 「計画的付与制度」 を導入している会社は、あらかじめ特定日を休みに設定可能(労使協定が必要)
- 時季変更権は個別判断 が大前提。会社都合で一律NGはアウト
- 使用者に求められる配慮:労働者の生活上の事情(結婚・出産・葬儀など)も考慮すべき
労働者の年次有給休暇の時季指定に対し、労働基準法の趣旨として、使用者は、できるだけ労働者が指定した時季に休暇をとれるよう状況に応じた配慮をすることが要請されているものとみることができるとするのが最高裁判所の判例である。 → 〇
過去問平成20年問5より
実際のところ、有給休暇の取得は完全に自由で、その取得の理由を問うものではないのが基本ですが、現実には事情によっては休ませたい、そんな理由で休むの??というモヤモヤは起こり得る。理由によって否定するのはNGで、ブラック企業まっしぐらなので気を付けましょう。
まとめ
- 有給は原則、労働者が自由に取得できる
- 会社が拒否できるのは「時季変更権」を行使する場合のみ
- その際も、代替要員の確保など会社側の努力が前提
- 「繁忙期だから一律不可」は法律上認められない
社労士試験でも頻出のテーマであり、実務では労働者の心情も混ざってトラブルになりやすい分野です。
労働者としては「有給は権利」という認識を持ちつつ、会社側としては「時季変更権の範囲」を理解して適切に運用することが大切ですね。
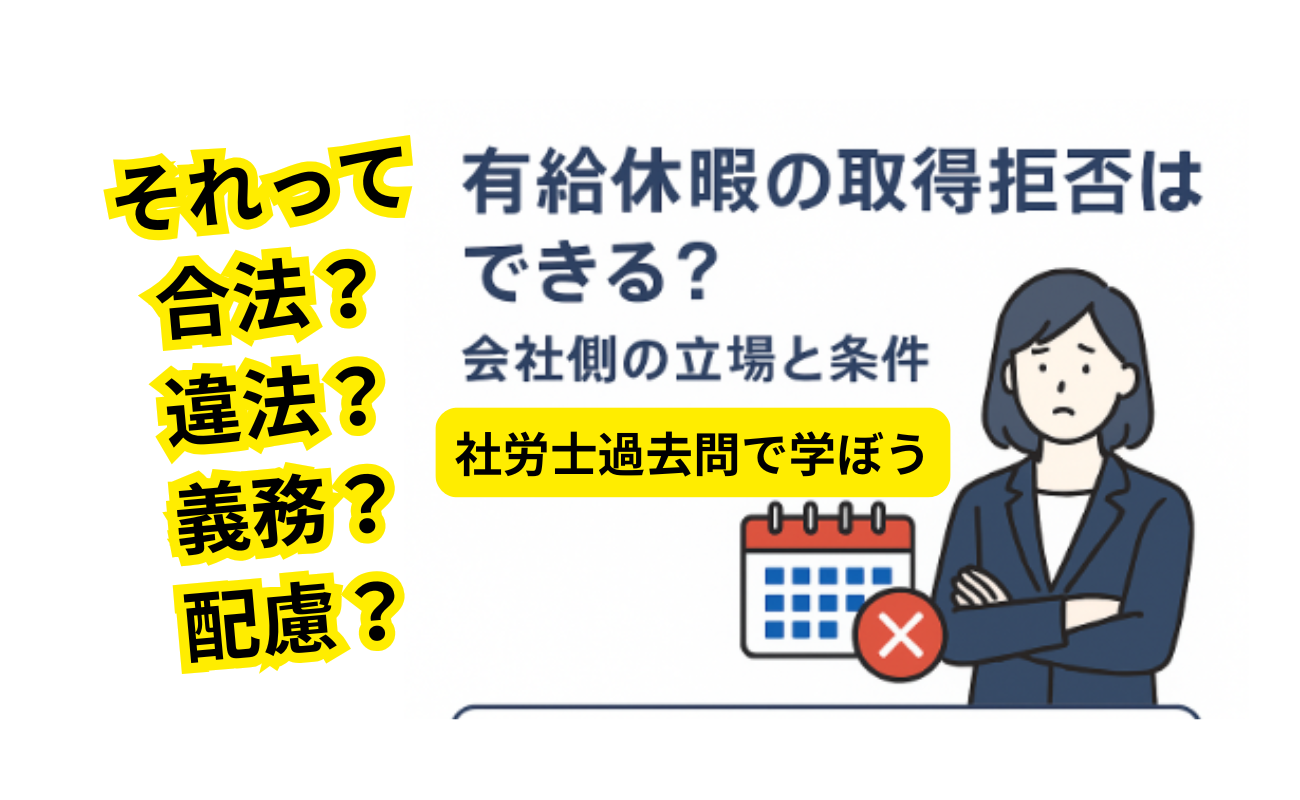




コメント