※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています
「社労士試験に合格したいけど、仕事が忙しくて勉強時間が取れない…」
「独学だとどのくらい勉強すればいいのか、そもそも合格できるのか不安…」
もしあなたが今、そうした悩みを抱えているなら、この記事はあなたのためのものです。私自身も会社員として働きながら、独学で社労士試験に合格しました。その経験から、働きながらでも確実に合格を掴むための、具体的な勉強時間確保のコツと戦略を、余すところなくお伝えします。
結論からお伝えします。
社労士試験は、働きながら、独学でも合格できます。
鍵となるのは、「勉強時間の絶対量を確保すること」と「質を極限まで高めること」の2つです。
働きながら合格に必要な勉強時間の目安
まず、働きながら独学で合格するためには、どのくらいの勉強時間が必要なのでしょうか。
一般的に、社労士試験の合格に必要な勉強時間1000時間と言われています。これはあくまで目安であり、法律知識の有無や学習効率、お仕事の業種などによって変動しますが、この独学合格まで1000時間という数字を一つの目標に設定することをおすすめします。
では、この1000時間を、働きながらどのように捻出するのか。
例えば、1年で合格を目指す場合、1日あたりの勉強時間は約2.7時間となります。
- 1000時間 ÷ 365日 = 2.73時間/日
2.7時間と聞くと、少し大変に感じるかもしれません。しかし、これを「平日」と「休日」に分解してみましょう。
- 平日: 1日あたり2時間
- 休日: 1日あたり6時間(週末2日で12時間)
この計画を立てると、平日は仕事から帰って2時間勉強し、土日でまとめて勉強時間を確保するというスタイルが見えてきます。これは1年での数字。
1年半、2年と初学から年数を重ねると1日当たりの時間は低減し、基礎固めをさらに進めたり、法改正や白書・統計問題に注力することもできるようになったりもするでしょう。
忙しい社会人のための勉強時間確保術
では、1年間での独学計画をどうやって実行していくか。ここからは、具体的な時間確保のテクニックを5つご紹介します。
1. 通勤時間を「最強の勉強時間」に変える
往復の通勤時間を、ただ電車に揺られているだけの時間にしてはいけません。スマートフォンやタブレットを活用して、音声学習や過去問演習の場に変えましょう。
- 電車: 語学アプリのように、法改正のポイントや重要条文を音読してくれるアプリを活用する。Youtubeでの条文聞き流しなどいいですね。
- 徒歩: 録音した講義を聴きながら歩く。
満員電車でテキストを開くのが難しい場合でも、音声学習なら可能です。毎日往復1時間の通勤時間があれば、それだけで年間365時間の勉強時間を確保できます。
2. 「朝活」で仕事前の集中力を最大化する
仕事で疲れた夜よりも、朝のほうが脳がクリアで集中しやすいという人は多いです。仕事が始まる前の1時間、早起きして勉強する習慣をつけましょう。朝の1時間は、夜の2時間にも匹敵するほどの集中力が得られます。
- ポイント: 前日に勉強する内容を準備しておくこと。朝起きてから「何をやろう…」と迷う時間をなくすことで、スムーズに学習を開始できます。
3. 昼休みを「スキマ時間」の宝庫にする
会社の昼休みは、たった数分でも貴重な勉強時間です。食事を終えた後の15~30分間を有効活用しましょう。
- 過去問の1問集中演習: 15分あれば、過去問を2~3問解くことができます。
- ノートの見直し: 暗記項目や苦手な分野をまとめたノートを読み返す。
4. 「スマホ断ち」で集中力を守る
勉強中にLINEの通知が来たり、SNSを見てしまったり…社会人は誘惑が多いです。スマホを物理的に遠ざける、もしくは勉強中は通知をオフにするなど、意識的に「スマホ断ち」を実践しましょう。スマホをオフにするだけで、あなたの集中力は格段に向上します。
5. 勉強時間を「可視化」する
勉強時間を記録するアプリやノートを活用しましょう。自分がどれだけ勉強したかが見える化されると、モチベーションの維持につながります。
- 通信教育であったり、資格勉強アプリなどは、勉強時間を記録・進捗管理や期日の管理ができ、講師への質問できるため、独学の孤独感を軽減してくれます。
4月になったら、直前期に、残された時間などを計算することで見えてくることもあるでしょう。
独学だからこそ意識したい「勉強の質」を高める戦略
時間を確保するだけでは不十分です。確保した時間をいかに効率的に使うかが、独学合格の鍵を握ります。
1. インプット(講義・テキスト)とアウトプット(問題演習)のバランス
「テキストを読むばかりで、なかなか問題が解けない…」という悩みは、独学者に多いものです。インプットとアウトプットのバランスを意識しましょう。
- 理想のサイクル: テキストを読んだら、すぐにその章の過去問を解く。
- 復習: 間違えた問題は、なぜ間違えたのかをテキストに戻って確認する。この作業を繰り返すことで、知識が定着しやすくなります。
2. 苦手科目を「見える化」する
自分がどの科目が苦手か、どの分野で失点しやすいかを把握することが大切です。
- 方法: 模試や過去問演習の結果を、科目ごとに記録する。
- 対策: 苦手科目には時間を多めに割き、得意科目で安定して点数を取れるようにする。
3. 「完璧主義」は捨てる
「この章を完璧に理解してから次の章に進もう」と考えていると、いつまでたっても先に進めません。最初は8割程度の理解で次に進み、問題演習で間違えた箇所を復習することで、理解を深めていくほうが効率的です。
最近の社労士試験の傾向としては問題文の文字数が多いため、読みだけでも結構時間を取られます。
最終的な結論
「社労士 独学 勉強時間 社会人」という道は、決して楽な道ではありません。しかし、適切な時間管理と質の高い学習戦略を組み合わせれば、十分に合格を掴める道です。
大切なのは、「時間がない」と嘆くのではなく、**「どうすれば時間を捻出できるか」**を考え、行動することです。
今日から、通勤時間を活用したり、朝少しだけ早起きしたり…小さな一歩から始めてみましょう。その一歩一歩が、必ずあなたの合格へと繋がります。

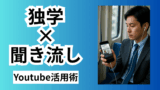


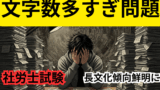
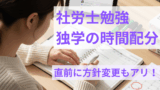




コメント