※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています
36協定とは
社労士試験でよく問われる労基法上の論点、36協定。
いわゆる通称である36協定(さぶろくきょうてい)は、労働基準法第36条に基づいており、企業が従業員に残業や休日労働を命じる際に必要となる「時間外労働・休日労働に関する協定届」のことです。
試験問題的には労働協約(過半数以上労働組合)との間で結んだものがあれば事業場全体に効果は及ぶか?とか
届出をすることで効果が生ずるとか
免罰効果というワードが飛び交うなどさまざまな切り口で出題されたりします。
次の論点に来るのは?
労働基準法上、時間外労働や休日労働をさせることができる「対象期間」は1年間と決まっています。
毎年1回、労働基準監督署に届出を行う必要がありますね。
自動更新条項がある場合であっても、翌年、協定の内容に変更がなくても更新し、労基署への提出が必要です。 実務上そうしていないようななあなあにしているようなところはNGでありブラックかしらね。
時間外労働時間について36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上 限」などを決めなければならない、といった定義めいた部分も重要。
今後掘り下げた内容や長文化して読ませる問題に発展する可能性もありますね。
予想問題と論点
36協定は1年間を対象期間とするのが原則ではあるが、3年とすることもできる。
× できません。1年更新です。
36協定は、3ヵ月間の期間を定めることができる。
○ 有効期間は、最も短い場合でも1年間となるが、1日及び1日を超え3か月以内の期間について定められた延長労働時間の有効期間までもすべて一律に1年間としなければならないものではなく、1日及び1日を超え3か月以内の期間について定められた延長時間の有効期間を1年間についての延長時間の有効期間とは別に、1年未満とすることもできる。
実際の実務上では、とりあえず1年で出しておいてよ、というのがリアルではあるのだけれども、半年で事業たたむから6か月の有効期間・対象期間としてくれってことはないこともないってことで。
3年とかにしちゃダメ?とか、自動更新にするというのを認めて?と労基署に問い合わせても、弾かれますね。
1年で内容を確認、従業員に改めて周知して、過半数労働者代表を定めるなどの社内での手続きの中で労働基準や労働者の権利、事業主の義務などを再確認して見直しせよ、とのこと。
そういった実務上の部分と36協定のあり方などが問われることも出てくるかもしれません。
独学で過去問やりながら、次年度の問題を想像しながら勉強に取り組めるのは試験終わり後で少し時間に余裕がある時などがいいかもしれません。
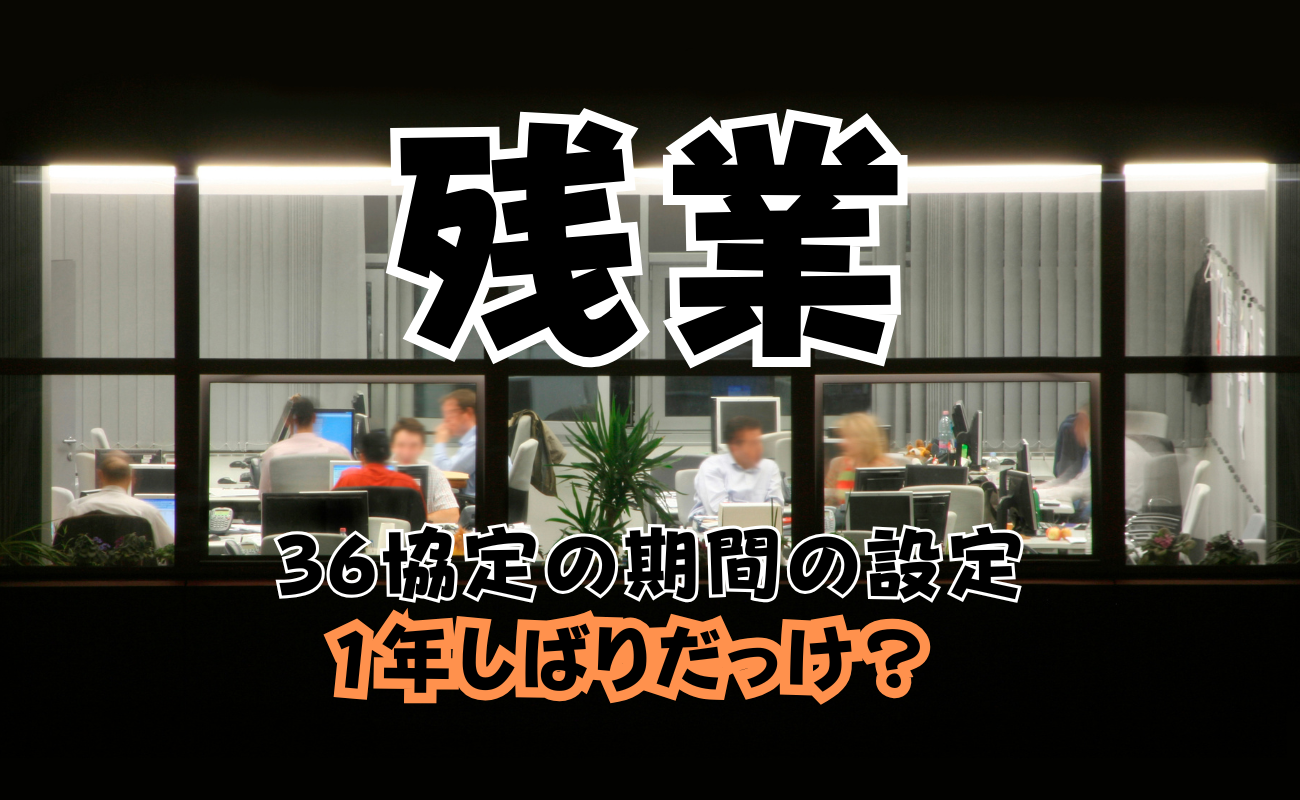

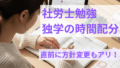
コメント