※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています
社労士試験、本番はここから! 4月以降の法改正攻略法
社労士試験を目指す皆さん、こんにちは! 4月になり、新しい年度が始まりましたね。 「今年こそは合格するぞ!」と気合を入れ直している方も多いのではないでしょうか。
「試験までまだ時間があるし、焦らなくてもいいか…」と思っている方もいるかもしれません。 しかし、実は 4月以降が合格に向けた本当の勝負どころ なんです! なぜなら、この時期に 試験範囲の確定 と 法改正論点の洗い出し が行われるからです。
1. 法改正は「差がつく」重要ポイント!
社労士試験では、毎年多くの法律が改正されます。 年金法、労働基準法、雇用保険法など、私たちの生活に密接に関わる法律が変わるたびに、試験範囲も更新されます。
例年は4月上旬までに施行された改正などが試験範囲に反映されます。
2025年度試験・令和7年度の社労士試験は、4月11日までに施行された法律 は、試験の出題範囲となります。 そのため、4月以降に発表される官報や厚生労働省の情報をチェックし、最新の法改正情報をキャッチアップすることが不可欠です。
法改正論点は、合否を分ける重要なポイントです。 多くの受験生が苦手にしがちな分野ですが、逆に言えば、ここでしっかり得点できれば、他の受験生に大きな差をつけられます。 過去問を完璧に解けても、法改正に対応できなければ、合格は遠のいてしまいます。
2. 効率的な法改正の学習法
では、具体的にどのように法改正を学習すれば良いのでしょうか?
① 情報をいち早くキャッチする
まずは、正確な情報をいち早く手に入れることが重要です。 予備校の講座やテキスト、ウェブサイト、専門誌などを活用し、最新の情報を常に追いかけましょう。
YouTubeで解説しているものも多くありますが、4月中旬以降にアップロードされた動画であることが大事でしょう。
厚生労働省や日本年金機構のウェブサイトも情報源として非常に有効です。
② 「改正前」と「改正後」を比較する
単に新しい条文を暗記するだけでは不十分です。 何が、どのように変わったのか を理解することが大切です。 改正前の制度や条文と、改正後のものを比較することで、なぜそのように変わったのか、その背景にある趣旨まで深く理解できます。 これにより、単なる暗記ではなく、理解に基づいた知識として定着させることができます。
③ 過去問と関連付けて学習する
法改正論点は、過去問には直接出てきません。 しかし、法改正の対象となった条文や制度に関連する過去問を解くことで、改正点の重要性を認識できます。 「この部分は改正されたから、今年はこう問われるかもしれない」という視点を持って、過去問を再確認してみましょう。
④模試の活用
社労士県の模試は各予備校や通信教育系で実施されています。模試の出版物などもありますかね。
最新の模擬試験では、法改正や最新の出題傾向を読み取った問題が出るため、過去問からの勉強のステップアップに活用出来ます。
法改正された部分がどのように問題に反映されるのか、そこに注目しながら模試に取り組むことで実践感覚を養えますね。
本試験を意識した出題の構成であるため、より実践的なものとして役に立つでしょう。
3. 合格への道は「積み重ね」
社労士試験は範囲が広く、覚えることも多いです。 しかし、焦る必要はありません。
4月以降に確定する法改正論点を一つずつ確実に押さえていくことが、合格への近道です。 この時期から、「日々の積み重ね」 を大切にしてください。
法改正のニュースをチェックしたり、予備校の法改正セミナーに参加したり、最新のテキストを読み込んだり、模試を受けてみて実践で力試しをしたり……小さな一歩が、合格へと繋がります。
さあ、4月から「本番」のスタートです!


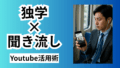
コメント