※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています
独学のペース配分
社会保険労務士試験に独学で挑戦する皆さん、日々の勉強お疲れ様です。
2025年8月に受験された方、結果発表を前に新たなスタートを切った方もいらっしゃるかもしれませんね!
独学でも合格可能と言われる社労士試験ですが、独学は自分のペースで進められる反面、「本当にこのやり方で大丈夫だろうか」「計画が思うように進まない」といった不安に直面することもあるでしょう。
独学のための勉強計画

合格への道のりを確実なものにするためには、羅針盤となる「勉強計画」が不可欠です。
独学者でも迷わず進める、具体的な勉強計画の立て方と進め方・そして方針修正の方法論をお伝えします。
ステップ1:ゴールと現在地を把握する
まず、あなたの「ゴール」と「現在地」を明確にしましょう。
- ゴール設定: 試験本番の日程をゴールとして設定し、そこから逆算して計画を立てます。ただ「合格する」だけでなく、「この時期までに基礎を固める」「この時期までに過去問を〇周する」といった具体的な中間目標を立てることが重要です。
- 現在地把握: 現時点で、どの科目に苦手意識があるか、得意な科目は何かを正直に書き出してみましょう。既に学習を始めている人は、一度模擬試験や過去問を解いてみるのも良い方法です。今の自分の立ち位置を客観的に知ることで、計画の精度が高まります。
ステップ2:全体像を把握し、学習期間を3つに分ける
社労士試験の独学は長期戦です。計画を立てる際は、ざっくりとでも良いので全体像を掴み、以下の3つの期間に分けましょう。
- 基礎固め期(試験の1年前〜半年前): 法律の全体像を理解し、科目ごとの繋がりを意識しながらインプットを行います。テキストを読み込み、簡単な問題集を解いて知識の定着を図ります。
- 過去問・応用期(試験の半年前〜直前期): この時期から本格的に過去問演習を開始します。ただ解くだけでなく、なぜ間違えたのかを丁寧に分析し、弱点を見つけ出して克服することが大切です。当サイトの過去問解説も活用してください。
- 直前総仕上げ期(試験1ヶ月前〜本番): 新しい問題には手を出さず、これまでに解いた過去問や模擬試験の復習、法改正点のチェックに集中します。最後の追い込みで、知識を再整理し、自信を持って本番に臨む準備をします。
ステップ3:具体的な週単位・日単位の計画を立てる
全体像が掴めたら、それを週単位、そして日単位の具体的な行動計画に落とし込みます。
- 週単位の計画: 「今週は労働基準法と労災保険法のテキストを読み終え、一問一答を解く」といった形で、無理のない範囲でタスクを設定します。週末に1週間の進捗を振り返る時間を設けることで、計画の修正点が見えてきます。
- 日単位の計画: 「朝起きたら30分、健康保険法の一問一答を解く」「夜は2時間、労働基準法のテキストを読む」など、具体的な行動をスケジュールに組み込みましょう。通勤時間や休憩時間も有効活用できるタスク(例:当サイトのスマホでできる一問一答など)を割り振ると、さらに効率が上がります。
ステップ4:計画は「守る」より「修正する」もの
最も重要なのは、計画は「守る」ことではなく、「修正する」ためにあると考えることです。
完璧な計画は存在しません。体調を崩したり、仕事が忙しくなったりして、計画通りに進まない日は必ずあります。そんな時、「もうダメだ」と諦めるのではなく、どこで遅れが生じたのかを冷静に分析し、次の週の計画を調整すれば良いのです。
計画を立て、それを進捗に合わせて柔軟に修正していくプロセスこそが、独学を成功に導く最大の秘訣です。
独学をサポートする物の活用
独学では隙間時間を捻出するのも大事だし、その生み出した隙間時間で直ぐにスタート切って取り掛かるのも大事。
やる、すぐやる、1秒で始める!みたいなのが大事です。
準備やセッティングで時間を浪費せずにすぐに!
ということで、聞き流し系のコンテンツは結構有効だったりします。
テキストや問題集をセットするまでの時間をYoutubeで条文読み上げを再生するとか、時間を無駄にしない意識が大事。記憶の定着に繋がります。
時期による修正
基礎固めの目安、どの程度の理解や得点力が・・・?というのは人それぞれ過ぎて難しいですね。
過去問を何周回せば、とかも一つの目安です。初学者ではまず答えを見ながらでも全科目1周やってみるのが大事で、模試までに3周程度はやっておければよいでしょう。
4月以降は改正や白書・統計などの最新情報チェック
ペース配分としては、毎年4月迄と4月以降を一つの境目として意識すると良い。
4月の初旬までの法改正が当該年度の試験範囲に含まれることになるため、4月を境に法改正や白書・統計情報などの最新情報のキャッチアップが大事になってきます。
過去問やりつつ最新の法改正についてもチェック、学習の忙しさが上がって来るので、ペースアップしたいところです。
模試は活用しよう
各種独学者向けの模試などもあります。
予備校主催の公開模試や、通信教育系の在宅模試、テキストとして売られている模試などもありますかね。無料の模試を開催している所も年度によってはあったような気もします。
多くの模試は、その年の5月~8月初旬くらいまでに行われていて、最新の法改正や白書情報などを反映した良質な予想問題として活用出来ます。
法改正の内容だけではイマイチどんな風に出題されるか分からなくても、模試で問題形式で出されると本番での出題イメージが付きやすく、理解も捗るでしょう。
直前で時間が足りない時には・・・
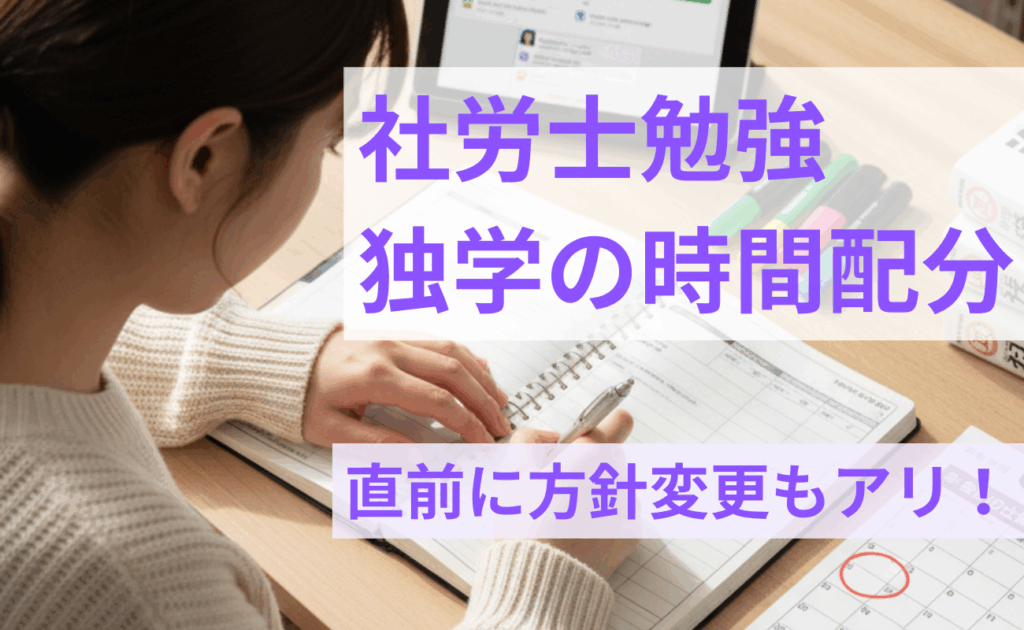
4月以降の学習で巻き返しが難しいこともあるでしょう。
仕事やプライベートでどうしても独学学習時間が取れないということもある。
そういった場合には、ある程度割り切って学習するしかないで、ヤマを張るとかしたいところですが、社労士試験の試験範囲は広大で膨大でヤマ張るとか考える時点で相当網羅的に勉強していないとムリ。
お持ちのテキストや過去問、受験した模試の問題用紙など、その中から学習の理解度や進捗に応じてある程度絞っていくことになる。
初学者の場合であれば基礎・出題頻度の高いところ・過去問の難易度の低い問題を中心に基礎問題での点数獲得を狙う方針にするとか。
2~3回受験した方であれば、過去問と模試を何とか網羅的に解くとか。
受験回数多く中々合格できない方は過去に選択式で後1点!とかで泣いていたりもするでしょうから、法改正や白書・統計と模試などの新し目の問題に触れるようにするとかね。
学習の段階や進捗に合わせて、重点を置くようしに、取り組んだ部分で本試験で得点できるように集中していくと良いでしょう。
マークシートだし、受ければ受かる可能性があるのが社労士試験、仮に合格できなくても直前に重点的に取り組んだ部分で得点を取れれば、次につながる自信にもなりますよ。
おわりに
独学は孤独な戦いかもしれませんが、明確な計画を持つことで、あなたの学習はより有意義で、確実なものになります。
ぜひ、この記事を参考に、あなただけの「合格へのロードマップ」を描き、自信を持って学習を進めてください。応援しています!
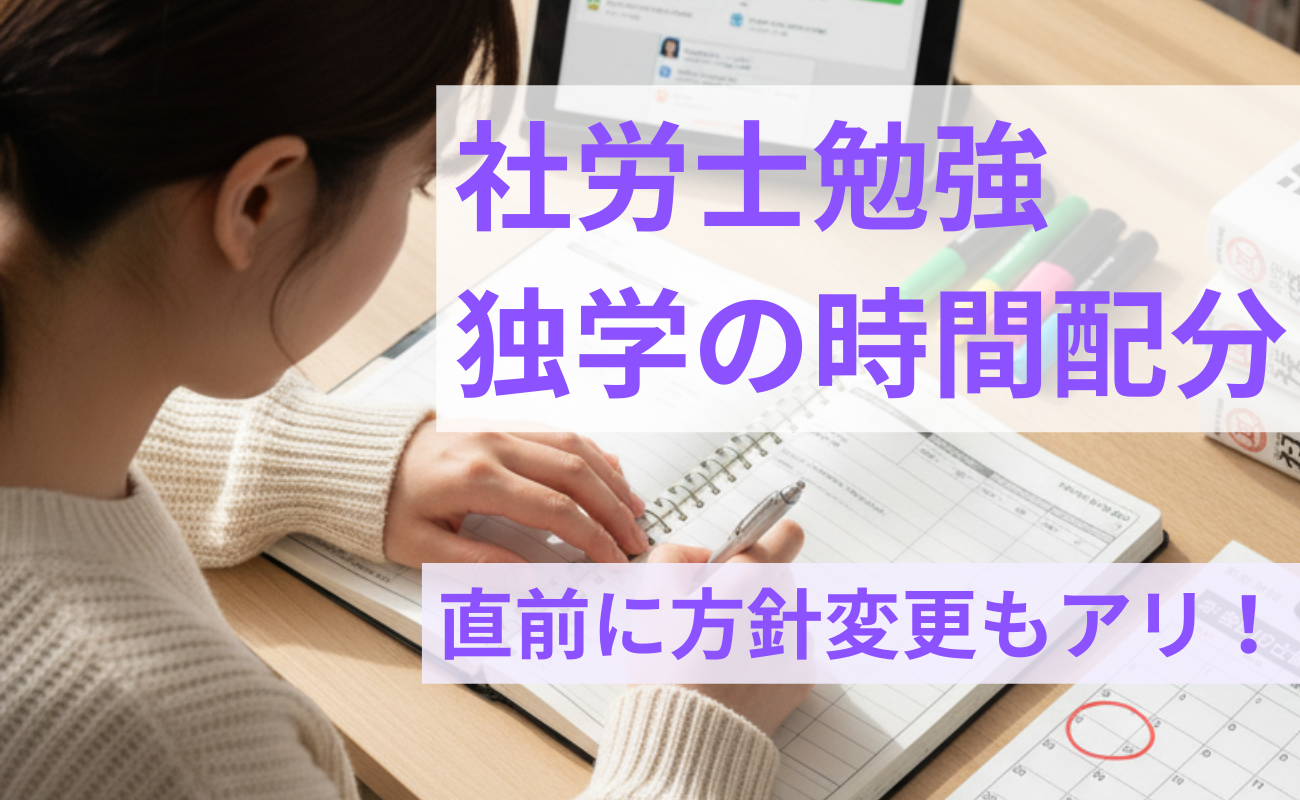
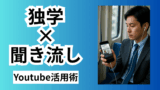



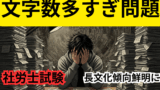


コメント