※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています
はじめに 使用者とは、というところ
社労士試験の労働基準法では、冒頭条文にあたる 第10条(使用者の定義) がしばしば出題されます。
条文自体を問うものから、「誰が使用者にあたるのか」という判例や事例を背景にした応用問題まで、試験の常連テーマです。
年を追うごとに、新しい問題ほど応用的なものになったり、長文化する傾向はあるのかも。
ここでは、実際に出題された過去問をピックアップし、設問文を完全掲載したうえで、正誤と解説をまとめます。
1. 労働基準法第10条(条文)
この法律で「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
つまり、「事業主」、「事業の経営担当者」、「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」の3つが
- 事業主本人(会社そのもの、個人事業主など)
- 経営担当者(代表取締役など経営を担う者・経営の決定権を持っていて報酬が高いイメージ)
- その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
この3つが「使用者」となりえます。
2. 過去問ピックアップ
令和6年(2024年) 択一式 労基 問2をアレンジ
設問文:
労働基準法において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
正解は
×
解説:
確かに賃金支払い者は典型的に「使用者」ですが、それに限りません。賃金を直接支払う立場になくても、労働条件の決定や人事権を行使する者も「使用者」に含まれます。
試験では「賃金を支払う者=使用者」と単純化して書いてある肢は誤りと判断しましょう。
この問題文の文章、ソレっぽいのですが、労働契約法の定義ですね。労契法では「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」に限定され、そのため、労働基準法の使用者よりも範囲が狭く、法人の場合は法人自体が使用者となるのです。
混同しないようにね。
3. まとめと試験対策のヒント
- 事業主=法人そのもの(又は個人事業主)
- 使用者=事業主+経営担当者+労務管理担当者
- 「賃金を払う者=使用者」と断定した肢は誤り
- 判例でも、人事権を持つ部長クラス(責任がある立場)は「使用者」にあたるとされる
労基法の最初の部分に出てくる基本概念ですが、択一式では引っかけ要素が多いテーマです。
独学だと次はこんな問題がくるかな??と過去問解きながら予想するのも大事かもしれません。模試などでは少しひねった問題もあるので、予想問題としては面白いかも。
条文暗記だけでなく、事業主と使用者の範囲の違いをイメージで整理しておきましょう。
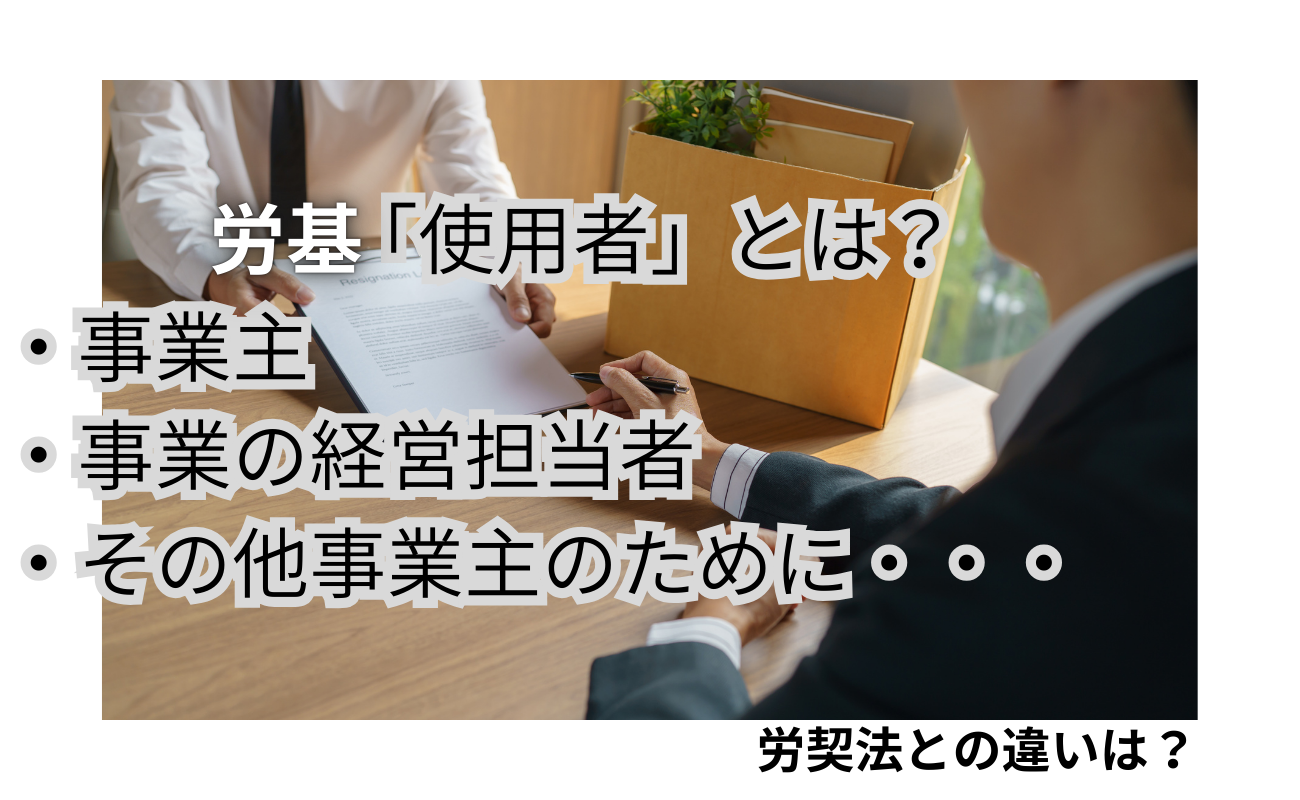
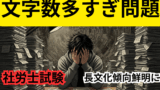
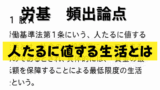
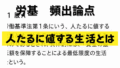

コメント