※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています
2026年に向けて、学びを再スタートする理由
社労士試験は 「選択式」と「択一式」 の2つの形式から成り立ち、合計 10科目 をバランス良く得点する必要がある試験です。
令和7年度の試験を受験したのであれば、早めに自己採点して弱点となってしまった科目、点数を落としてしまったジャンルなどの整理をしましょう。
この広大な範囲や弱点の認識が、再開に向けた大きなハードルにもなりますが、科目ごとに整理しながら段階的に進めることで、着実にモチベーションを取り戻せます。
科目を「系統別」にまとめて、学習の道すじを明確にする
社労士試験の科目は大きく 労働関係 と 社会保険関係 に分かれます:
① 労働関係科目(6科目)
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労災保険法
- 雇用保険法
- 労働保険の徴収関連法
- 労務管理その他の一般常識(法規・統計含む)
② 社会保険関係科目(4科目)
- 健康保険法
- 厚生年金保険法
- 国民年金法
- 社会保険に関する一般常識(法規・統計含む)
まずは自分が得意—or苦手—な系統を見つけてスタート地点を選びましょう。直近の試験の自己採点や、模試などでの点数分布などでチェックするのも大事です。
たとえば、法律ベースが得意なら労働関係、数字や統計が得意なら社会保険関係から進めると、再開の第一歩がよりスムーズです。
早いスタートで有利に進めたい!最新の学習状況
- 合格率は約6〜7%で推移しており、依然として「10人に1人しか合格しない」難関試験です。でも、その分「しっかりとした学習計画と継続」が成功への鍵になります。
- 2024年度・2025年度の選択式の合格基準点は合計40点中、25〜27点前後(各科目3点以上が条件)まずは、「6割~7割の得点確保」を目標に、科目ごとの基準点クリアを目指しましょう。
学習計画の立て方:モチベーションを維持するために
- 短期目標を設定
例:「まずは労働基準法を中心に5日間で選択式攻略」など、小さな成功を積み重ねていきましょう。 - 得意科目から着手
得意な科目(例:厚生年金・労基など)でスタートすると、進捗の実感が得やすく、勉強再開の勢いを取り戻せます - 苦手科目の対策を”選択式”から
選択式はつまずきやすい一方、一部「救済科目」が該当すると合格が救われるケースもあります 。まずは選択式の“穴を埋める”学びから始めるのも一つの戦略です。 - アウトプット学習を優先
テキスト読みなどの覚えるのに時間を充てるより「問題を解く」習慣をつけることで、効率的に記憶が定着します。 - 情報更新は欠かさずに
法改正や出題傾向の変化に敏感になり、最新のテキストや講義を活用しましょう 特に2026年4月上旬以降、法改正範囲が確定してからがスパートになります
学びを続けるためのコツ:モチベーションの立て直しに効く
- 自分の進捗を可視化
例:「今日は労基の条文2つ、問題演習10問クリアした!」と記録するだけで、頑張りが形になります。 - 成功体験を振り返る
過去に得意だった科目・アプローチを思い出すことで、自信が再び湧いてきます。 - 小さなご褒美を設定
「5日間継続できたら好きなカフェで休憩」など、息抜きの時間を作ることが長続きのコツです。
まとめ
| ステップ | 実例 |
|---|---|
| ①系統を決める | 「法律系からスタート」「数字系が得意だから保険科目」 |
| ②小さな目標設定 | 「3日で労基選択式を全問通しで解く」 |
| ③アウトプット中心に学ぶ | 「条文 → 問題演習をセットで」 |
| ④進捗を記録&振り返り | 「問題集1章クリア」→「達成感が得られた」 |
| ⑤こまめに情報アップデート | 法改正や模試の傾向にも注目! |
あなたが再び学習を始めるその瞬間から、未来への道はまた開かれます。 広大な10科目も、「系統別+科目別+小さなゴールを積み重ねる」ことで、確実にクリアできる挑戦です。
2026年版社労士試験への新スタートとして、ぜひこの記事を参考にして、前に進んでいきましょう!

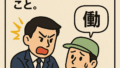
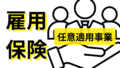
コメント